医療の最前線から学ぶ専門情報ブログ
〜医師の視点でお届けする健康ケアお役立ち情報〜
Dr.脇坂 VOL.02
忘年会シーズンの肝臓ケア。二日酔い予防と正しいリカバリー
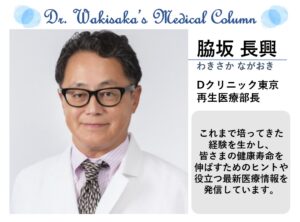
年末が近づいて、会食や忘年会などお酒を飲む機会が一気に増えました。
普段は節制していても、この時期ばかりは飲み疲れを感じる日が多くなります。
皆さんはどうでしょう?
飲み会が続く季節こそ、肝臓をいたわる意識がとても大切です。
連日の飲酒が肝臓にかなりの負担をかけるのは、みなさんご存じの通り。
しかし、肝臓は沈黙の臓器と呼ばれるくらい、多少のダメージがあっても、何も自覚症状を感じさせない臓器なのです。
また、肝臓は自覚症状が無いまま、知らぬ間にダメージから回復する能力を持っています。
そんな肝臓でも、休む間もなく働き続ければ、機能が低下し、倦怠感や肌荒れ、食欲不振といった目に見えるサインが現れます。
不調を感じたなら早急に病院を受診すべきですが、体調の変化が出る前に自身で酒量を調節しましょう。
冬は二日酔いになりやすい?
冬は二日酔いになりやすいと聞いたことがあったり、ご自身でも感じたりすることはありませんか?
連日の飲み疲れはともかく、冬は実際に二日酔いになりやすい要素がいくつもあります。
外気温が低い冬は、体温を維持するためにエネルギーを多く使います。
そのため、アルコールを分解する酵素の働きにも影響が出て、肝臓のアルコール代謝速度が遅くなります。
また、暖房による乾燥が引き起こす脱水や寒さによる血流の低下のため、肝臓でのアルコール代謝が遅れ、翌朝まで飲酒の影響が残ってしまうのです。
更に、日照時間が短い冬はメラトニンの分泌リズムが乱れやすく、睡眠の質が下がることで、ダメージを受けた肝臓の修復のための時間も短くなります。
二日酔いのメカニズムを理解する
アルコールは、体内で「アルコール → アセトアルデヒド → 酢酸 → 水と二酸化炭素」という流れで分解されます。
この途中に生じるアセトアルデヒドは、頭痛・吐き気・動悸・顔の赤みなど二日酔いの主な原因になります。
日本人の約4割は、遺伝的に、このアセトアルデヒドを分解する酵素(ALDH2)の活性が低いかまたはほとんど働かない体質です。
そのため、アルコールの代謝が遅く、体内に有害物質が長くとどまるのです。
お酒に強い人・弱い人で肝臓への影響は違う?
お酒に強い人はアルコール代謝が早い反面、アルコール分解の過程で活性酸素が多く発生し、肝細胞が酸化ストレスで傷つきます。
お酒が弱い人はアセトアルデヒドが長く体内に残り、むくみや顔の赤みが出やすくなるだけでなく、肝臓での代謝時間は長くなります。
つまり、どちらのタイプでも、お酒を飲みすぎれば肝臓は疲弊するのです。
医療機関でのサポート:肝機能強化点滴という選択
「やってしまった…」と後悔するほど飲みすぎてしまう夜、誰にでもあります。
大事な仕事や予定があるときは、どうにか早く回復したいと思うもの。
そんなときは、無理に我慢したり自己流で乗り切ろうとしたりせず、医療機関にサポートを求めてください。
肝機能強化点滴は、アルコールの分解を促進するとともに、倦怠感や頭痛をやわらげてくれます。
Dクリニック東京では、医師の管理のもとで安全に点滴を行い、「最悪の朝」をできるだけ早くリセットし、できるだけ早くパフォーマンスを取り戻すサポートをしています。
肝機能強化点滴(二日酔い改善)や疲労回復点滴、抗酸化点滴などの点滴治療は、仕事やプライベートでベストコンディションを求める方にとって、頼れるリカバリー手段のひとつです。
肝臓を守るための工夫・飲み方・生活習慣
飲酒中はこまめに水を飲む
アルコールには利尿作用があり、お酒を飲んだ量より多い水分が体から出ていきます。
脱水状態では、アルコール分解に必要な酵素がうまく働きません。
お酒1杯に対して水グラス1杯を目安に飲めばアルコール代謝がスムーズになり、二日酔い予防につながります。
空腹で飲酒しないようにする
空腹時にお酒を飲むと、アルコールが胃や小腸から血液中に急速に吸収されます。
アルコールの血中濃度の急激な上昇は、肝臓に大きな負担をかけます。
チーズや枝豆、豆腐などタンパク質や脂質を少し摂ってから飲酒すれば、アルコールの吸収はゆっくりになるので、飲み会の前には少し何かつまんでおくことをおすすめします。
夜遅い食事を控える
飲酒後の「締めのラーメン」や揚げ物は、アルコールと一緒に脂肪をため込みやすく、脂肪肝のリスクを高めます。
どうしても何か食べたい場合は、味噌汁・おにぎり・スープなど軽めのもので済ませて、少量の塩分と水分を同時に補ってください。
休肝日を設ける
肝臓は再生能力の高い臓器ですが、ダメージを受けた幹細胞が一晩で完全に回復するわけではありません。
週に2日アルコールを摂らない「休肝日」を設けることで、肝臓の修復が進み、アルコール分解酵素の働きも安定します。
毎日お酒を飲む人なら、2日連続の休肝日を作ると回復効果が高まります。
適量を守る
アルコールの適量は「純アルコール量」で1日20g程度が目安です。
ビール中瓶1本(500ml)や日本酒1合、ワインならグラス2杯ほどに相当します。
これを超える飲酒を続けると脂肪肝や高血圧、糖代謝異常などの疾患が発症したり、肝機能の乱れが起こりやすくなります。
「少し物足りないくらいでやめる」意識が、肝臓の健康を長く保つ秘訣です。
翌日の正しいリカバリー法
飲みすぎた翌日は、肝臓を休ませながら代謝を促すことがポイントです。
無理に急がず、ゆっくり身体のペースを整えましょう。
まずは、水分とミネラルをしっかり補う
アルコールの分解には多くの水分と塩分が使われます。
二日酔いの解消には、経口補水液のほか、味噌汁、スープなど、温かくて塩分を含む飲み物が適しています。
冷たい水よりも常温や温かい飲み物の方が吸収がスムーズで、胃にもやさしいです。
朝は糖質とたんぱく質を意識
お粥と豆腐、卵といったメニューの朝食や、朝食替わりのバナナが肝臓の修復を助けます。
脂っこい料理や刺激物は避け、消化の良いものを選びましょう。
カフェインは控えめに
コーヒーや紅茶には利尿作用があり、脱水を悪化させることがあります。
代わりに白湯やカフェインの少ないハーブティーなどを飲んで、体をゆっくり温めるのがおすすめです。
軽く身体を動かす
少し歩くだけでも血流が良くなり、肝臓での代謝が高まります。
外を歩く散歩は気分転換にもなり、頭の重さもやわらぐでしょう。
何より大切なのは睡眠
肝臓の細胞は、眠っている間により速く修復が進みます。
早めに就寝してしっかりと睡眠を取ることが、最良のリカバリーになります。
肝臓をいたわる意識が大きな違いに
お酒を楽しむこと自体は、決して悪いことではありません。
大切なのは「お酒とどう付き合うか」という意識です。
飲酒時は水も一緒に取りつつ、食事とともにゆっくりお酒を味わい、翌日は肝臓を休ませる。
そんなささやかな習慣の積み重ねが、お酒を楽しんだ翌日の目覚めや身体の軽さ、体調の良さとしてはっきり表れます。
忘年会が続くこの季節こそ、「楽しむ」と「いたわる」を上手に組み合わせて、大切なご自身の身体と上手に付き合っていきましょう。









